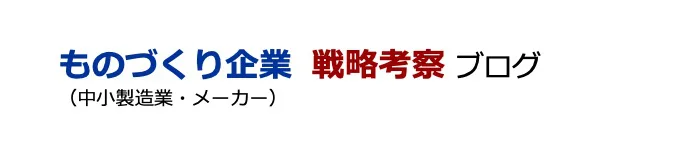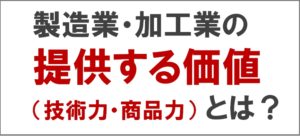重要だが、やらないこと
「スキルアップ」「教育」
製造業経営コンサルタントの井上です。
中小製造業の特に受託製造業、加工業は、自社製品がないので受け仕事であるので、日常の活動が自社の商品であると常々伝えております。
言い変えれば、自社の提供する価値です。
メーカーの場合は、開発力が重要になります。前提として、受託製造業・加工業同様に現場力が重要です。
受託製造業の「商品力」の中に、当然技術力も入ってます。
中小製造業が会社を強くしていくには、攻めと守りがあります。
今回は、守りについてです。(これが攻めるために重要な要素にもなります。)
受託製造業・加工業の「商品力」を見て頂いたと思いますが、マネジメントの部分がいいですが、技術力も当然あります。
その技術力が良い悪いとあるのですが、その前提条件の従業員のスキル(力量)が非常に重要です。
当たり前ですが、70~80名規模以下の会社では、スキルマップ(力量)が真剣に考えられており、明確になっている会社は少ないのではないのでしょうか?
私も、ISOを取得し運営している会社はありますが、やらなければいけないからやってますという会社がほとんどです。これが現実です。大手企業は、スキルも明確になっており、教育もされて、多能工も進み、更に機械の自動化も進み、システム化も進んでいます。
中小製造業は?
スキルアップがやらなければいけない理由が、単位が「個人」だからです。
もう少し分かりやすく言うと、マネジメントは組織で行うことなので、10人のうち2人が優秀ならなんとかなる場合があります。
スキルアップは、個人個人の能力を上げる必要があります。会社として、あらゆる教育する「場」や「ツール」などを用意できれば良いのですが、意識が高くない会社では「OJT」という名の放置です。
個々人のもともとの能力が低い場合、最悪、人材を募集しないといけない事態になります。また時間がかかってしまいます。
「マナジメント」は組織で動くので、一部の優秀なメンバーを中心に進歩ができ改善し易いですが、個人の能力アップである「スキル(力量)」は時間がかかります。
多能工化するにも、上司の仕事を部下に振っていくときでも、結局、他のメンバーのスキルが低いために、新しいやり方、体制を作り辛くなります。そして、今まで通りが続いてしまいます。
ぜひ、最終ネックになりやすい「スキルアップ」は、やって損はないことは間違いないので、重要事項として常に取り組んでいきまましょう。
デジタル時代の「ものづくりは人づくり」とは
< 目 次 > 第1回目:デジタル化時代の「ものづくりは人づくり」とは? 第2回目:今後の中小製造業の仕事は誰がやるのか? ◆「機械・ロボット」にさせる仕事 ◆「システム・AI」にさせる仕事 ◆「人間」がするべき仕事 ・誰でも出来る化 ・高度な専門職(職人) ・管理職 第3回目:中小製造業の人材育成・教育の実態 ◆大手に比べて人材の質も比較すると低く、教育の仕組み化も弱くのに教育していない現実 ◆OJTという名の丸投げ無責任体質で「教育品質」のバラツキが大きい ◆ISOでの形だけの教育計画 第4回目:「御社の社員の一人前基準・目安」は何ですか? ◆何が求められるスキルなのかを明確にする➜目次化 ◆職種別の一人前基準を明確にする ◆「一人前基準」は自発的に伸びる社員の道標になる ◆部品加工業におけるスキルマップの事例 第5回目:人材育成・教育は、コンテンツ化が重要。コンテンツ化して「資産化」しろ! ◆「目次」が出来たら、項目ごとに「コンテンツ化」しろ ◆デジタル化した「教育のコンテンツ化」はアップデート可能な「資産」 ◆「コンテンツ化」の手段としての「動画」活用 ◆「教育コンテンツ」+「教え方」もZoomのレコーディングを活用してデジタル化する ◆コンテンツのアップデートも考慮した「教育体系」がデジタル化時代には必要 第6回目:難易度の高い業務ほどOJTという名の人任せでなく教育方法を「研究」する ◆教育する事が良い事であると勘違いしている ◆難易度が低い業務ほどマニュアル化(明確化)されているが、なぜか難しい業務ほど人任せの現実 ◆習得に時間がかかる(難易度の高い)業務ほど、ノウハウの現場の職人依存の現状 第7回目:教育することも工数がかかる。教育工数を削減も ◆「コンテンツ化」すれば、教育する工数を減らせる(人が教えなくて良い状態」を作る) ◆教育の「コンテンツ化」=「教育する工数削減」=「技術伝承がしやすい環境」 第8回目:製造業の評価制度はスキルが明確でなくければ上辺だけに評価制度になる。(人材育成と評価制度の関連性)