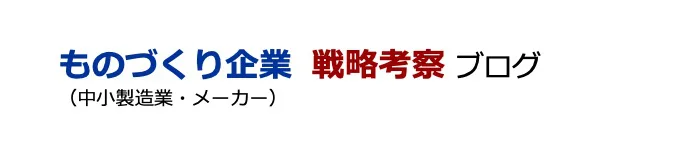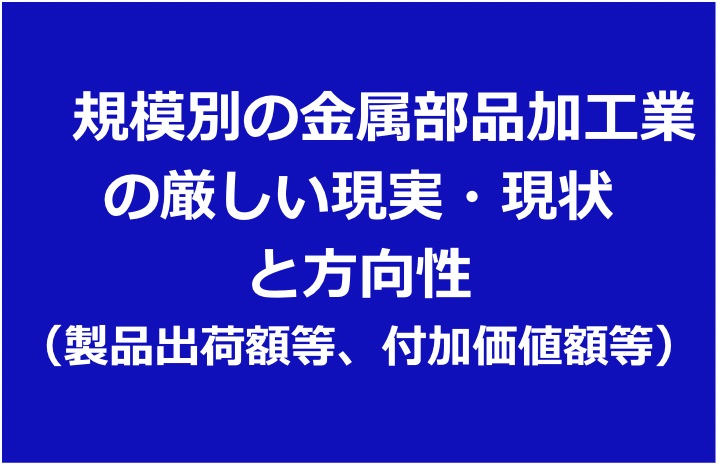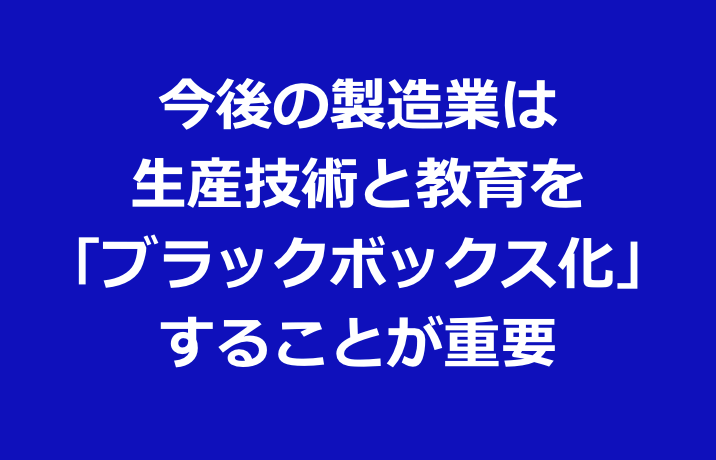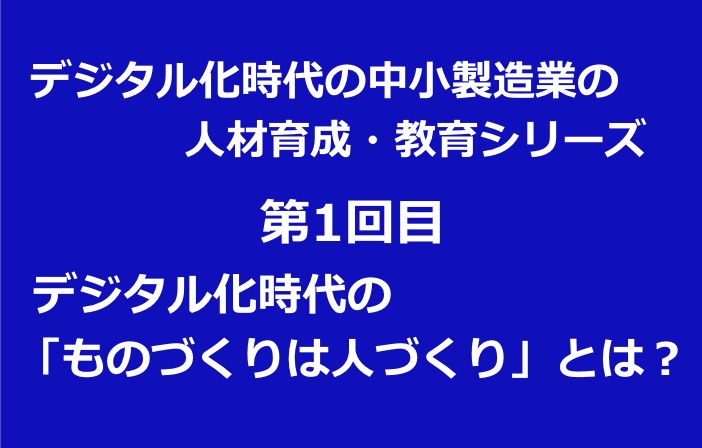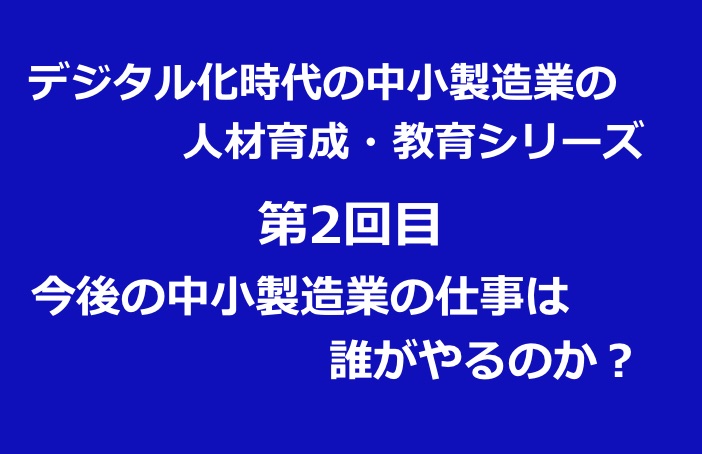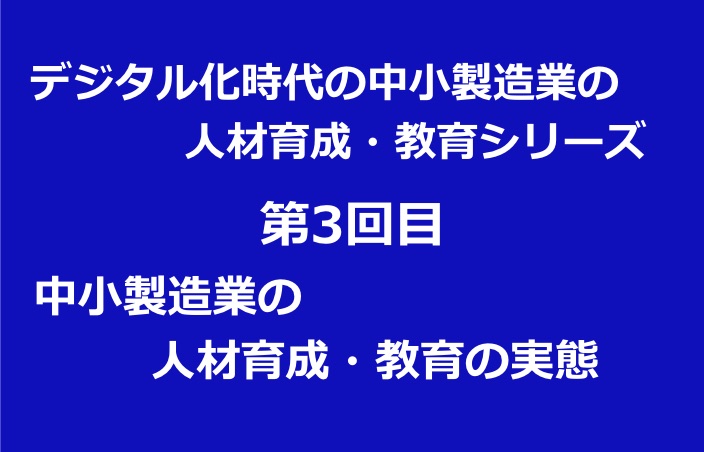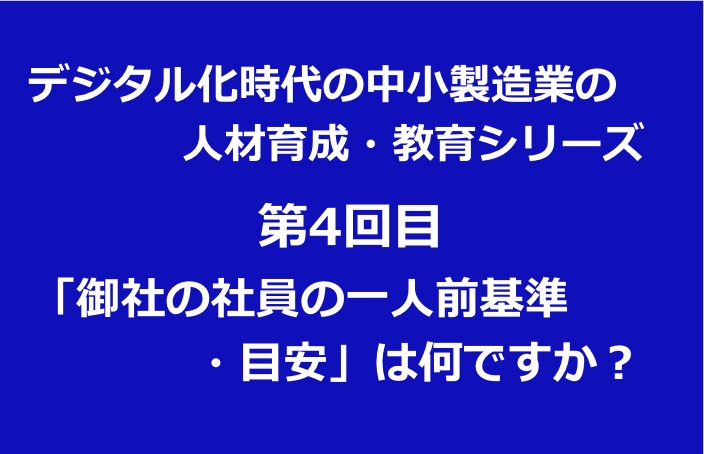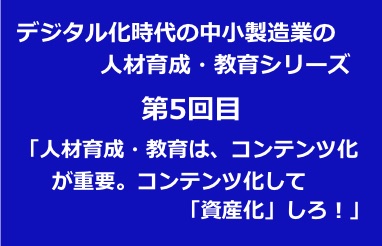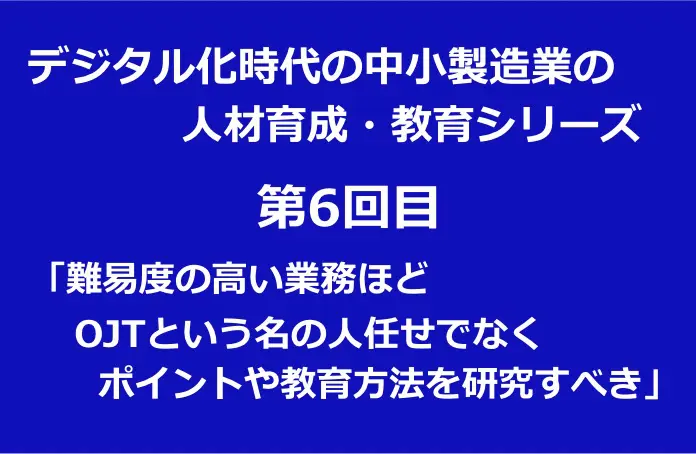デジタル化時代の中小製造業の
人材育成・教育シリーズ
第6回目 難易度の高い業務ほどOJTという名の人任せでなくポイントや教育方法を「研究」すべき
第6回目の「難易度の高い業務ほどOJTという名の人任せでなくポイントや教育方法を「研究」すべき」では、
●難易度が低い業務ほどマニュアル化(明確化)されているが、なぜか難しい業務ほど人任せの現実
●習得に時間がかかる(難易度の高い)業務ほど、ノウハウの現場の職人依存の現状
について述べてきました。
更に、機械化、システム化を誰でも購入できる資本力で決まります。ただ、お金があれば同じことができる、即ち差を付けづらくなります。差別化できる事としては、人間が行う難易度の高い業務しかないのですが、マニュアル化しづらいので、教育方法の研究に力を入れている会社が少ないです。
ぜひ考え方だけは、
●仕事をさせながら、教育する
↓
●教育しながら、仕事もさせる
●習得に8〜10年かかるから大変なんです
↓
●習得に8~10年かかるなら、5年以内でできれば3年以内に一人前にできないかチャレンジする
ここまでいかなくても、少しで会社が強くなる為の考え方を変えて、具体的な行動を起こして下さい。
実際に私のクライアントでは既に実施しており、その成果も多く出て来ています。ぜひ、御社にも取り入れて、強い会社を作るように頑張ってみて下さい。
第6回目の「難易度の高い業務ほどOJTという名の人任せでなくポイントや教育方法を「研究」すべき」では、
●難易度が低い業務ほどマニュアル化(明確化)されているが、なぜか難しい業務ほど人任せの現実
●習得に時間がかかる(難易度の高い)業務ほど、ノウハウの現場の職人依存の現状
について述べてきました。
更に、機械化、システム化を誰でも購入できる資本力で決まります。ただ、お金があれば同じことができる、即ち差を付けづらくなります。差別化できる事としては、人間が行う難易度の高い業務しかないのですが、マニュアル化しづらいので、教育方法の研究に力を入れている会社が少ないです。
ぜひ考え方だけは、
●仕事をさせながら、教育する
↓
●教育しながら、仕事もさせる
●習得に8〜10年かかるから大変なんです
↓
●習得に8~10年かかるなら、5年以内でできれば3年以内に一人前にできないかチャレンジする
ここまでいかなくても、少しで会社が強くなる為の考え方を変えて、具体的な行動を起こして下さい。
実際に私のクライアントでは既に実施しており、その成果も多く出て来ています。ぜひ、御社にも取り入れて、強い会社を作るように頑張ってみて下さい。
< 目 次 > 第1回目:デジタル化時代の「ものづくりは人づくり」とは? 第2回目:今後の中小製造業の仕事は誰がやるのか? ◆「機械・ロボット」にさせる仕事 ◆「システム・AI」にさせる仕事 ◆「人間」がするべき仕事 ・誰でも出来る化 ・高度な専門職(職人) ・管理職 第3回目:中小製造業の人材育成・教育の実態 ◆大手に比べて人材の質も比較すると低く、教育の仕組み化も弱くのに教育していない現実 ◆OJTという名の丸投げ無責任体質で「教育品質」のバラツキが大きい ◆ISOでの形だけの教育計画 第4回目:「御社の社員の一人前基準・目安」は何ですか? ◆何が求められるスキルなのかを明確にする➜目次化 ◆職種別の一人前基準を明確にする ◆「一人前基準」は自発的に伸びる社員の道標になる ◆部品加工業におけるスキルマップの事例 第5回目:人材育成・教育は、コンテンツ化が重要。コンテンツ化して「資産化」しろ! ◆「目次」が出来たら、項目ごとに「コンテンツ化」しろ ◆デジタル化した「教育のコンテンツ化」はアップデート可能な「資産」 ◆「コンテンツ化」の手段としての「動画」活用 ◆「教育コンテンツ」+「教え方」もZoomのレコーディングを活用してデジタル化する ◆コンテンツのアップデートも考慮した「教育体系」がデジタル化時代には必要 第6回目:難易度の高い業務ほどOJTという名の人任せでなく教育方法を「研究」する ◆教育する事が良い事であると勘違いしている ◆難易度が低い業務ほどマニュアル化(明確化)されているが、なぜか難しい業務ほど人任せの現実 ◆習得に時間がかかる(難易度の高い)業務ほど、ノウハウの現場の職人依存の現状 第7回目:教育することも工数がかかる。教育工数を削減も ◆「コンテンツ化」すれば、教育する工数を減らせる(人が教えなくて良い状態」を作る) ◆教育の「コンテンツ化」=「教育する工数削減」=「技術伝承がしやすい環境」 第8回目:製造業の評価制度はスキルが明確でなくければ上辺だけに評価制度になる。(人材育成と評価制度の関連性)
第6回目の「難易度の高い業務ほどOJTという名の人任せでなくポイントや教育方法を「研究」すべき」では、
●難易度が低い業務ほどマニュアル化(明確化)されているが、なぜか難しい業務ほど人任せの現実
●習得に時間がかかる(難易度の高い)業務ほど、ノウハウの現場の職人依存の現状
について述べてきました。
更に、機械化、システム化を誰でも購入できる資本力で決まります。ただ、お金があれば同じことができる、即ち差を付けづらくなります。差別化できる事としては、人間が行う難易度の高い業務しかないのですが、マニュアル化しづらいので、教育方法の研究に力を入れている会社が少ないです。
ぜひ考え方だけは、
●仕事をさせながら、教育する
↓
●教育しながら、仕事もさせる
●習得に8〜10年かかるから大変なんです
↓
●習得に8~10年かかるなら、5年以内でできれば3年以内に一人前にできないかチャレンジする
ここまでいかなくても、少しで会社が強くなる為の考え方を変えて、具体的な行動を起こして下さい。
実際に私のクライアントでは既に実施しており、その成果も多く出て来ています。ぜひ、御社にも取り入れて、強い会社を作るように頑張ってみて下さい。
第6回目の「難易度の高い業務ほどOJTという名の人任せでなくポイントや教育方法を「研究」すべき」では、
●難易度が低い業務ほどマニュアル化(明確化)されているが、なぜか難しい業務ほど人任せの現実
●習得に時間がかかる(難易度の高い)業務ほど、ノウハウの現場の職人依存の現状
について述べてきました。
更に、機械化、システム化を誰でも購入できる資本力で決まります。ただ、お金があれば同じことができる、即ち差を付けづらくなります。差別化できる事としては、人間が行う難易度の高い業務しかないのですが、マニュアル化しづらいので、教育方法の研究に力を入れている会社が少ないです。
ぜひ考え方だけは、
●仕事をさせながら、教育する
↓
●教育しながら、仕事もさせる
●習得に8〜10年かかるから大変なんです
↓
●習得に8~10年かかるなら、5年以内でできれば3年以内に一人前にできないかチャレンジする
ここまでいかなくても、少しで会社が強くなる為の考え方を変えて、具体的な行動を起こして下さい。
実際に私のクライアントでは既に実施しており、その成果も多く出て来ています。ぜひ、御社にも取り入れて、強い会社を作るように頑張ってみて下さい。
第6回目の「難易度の高い業務ほどOJTという名の人任せでなくポイントや教育方法を「研究」すべき」では、
●難易度が低い業務ほどマニュアル化(明確化)されているが、なぜか難しい業務ほど人任せの現実
●習得に時間がかかる(難易度の高い)業務ほど、ノウハウの現場の職人依存の現状
について述べてきました。
更に、機械化、システム化を誰でも購入できる資本力で決まります。ただ、お金があれば同じことができる、即ち差を付けづらくなります。差別化できる事としては、人間が行う難易度の高い業務しかないのですが、マニュアル化しづらいので、教育方法の研究に力を入れている会社が少ないです。
ぜひ考え方だけは、
●仕事をさせながら、教育する
↓
●教育しながら、仕事もさせる
●習得に8〜10年かかるから大変なんです
↓
●習得に8~10年かかるなら、5年以内でできれば3年以内に一人前にできないかチャレンジする
ここまでいかなくても、少しで会社が強くなる為の考え方を変えて、具体的な行動を起こして下さい。
実際に私のクライアントでは既に実施しており、その成果も多く出て来ています。ぜひ、御社にも取り入れて、強い会社を作るように頑張ってみて下さい。
第6回目の「難易度の高い業務ほどOJTという名の人任せでなくポイントや教育方法を「研究」すべき」では、
●難易度が低い業務ほどマニュアル化(明確化)されているが、なぜか難しい業務ほど人任せの現実
●習得に時間がかかる(難易度の高い)業務ほど、ノウハウの現場の職人依存の現状
について述べてきました。
更に、機械化、システム化を誰でも購入できる資本力で決まります。ただ、お金があれば同じことができる、即ち差を付けづらくなります。差別化できる事としては、人間が行う難易度の高い業務しかないのですが、マニュアル化しづらいので、教育方法の研究に力を入れている会社が少ないです。
ぜひ考え方だけは、
●仕事をさせながら、教育する
↓
●教育しながら、仕事もさせる
●習得に8〜10年かかるから大変なんです
↓
●習得に8~10年かかるなら、5年以内でできれば3年以内に一人前にできないかチャレンジする
ここまでいかなくても、少しで会社が強くなる為の考え方を変えて、具体的な行動を起こして下さい。
実際に私のクライアントでは既に実施しており、その成果も多く出て来ています。ぜひ、御社にも取り入れて、強い会社を作るように頑張ってみて下さい。
第6回目の「難易度の高い業務ほどOJTという名の人任せでなくポイントや教育方法を「研究」すべき」では、
●難易度が低い業務ほどマニュアル化(明確化)されているが、なぜか難しい業務ほど人任せの現実
●習得に時間がかかる(難易度の高い)業務ほど、ノウハウの現場の職人依存の現状
について述べてきました。
更に、機械化、システム化を誰でも購入できる資本力で決まります。ただ、お金があれば同じことができる、即ち差を付けづらくなります。差別化できる事としては、人間が行う難易度の高い業務しかないのですが、マニュアル化しづらいので、教育方法の研究に力を入れている会社が少ないです。
ぜひ考え方だけは、
●仕事をさせながら、教育する
↓
●教育しながら、仕事もさせる
●習得に8〜10年かかるから大変なんです
↓
●習得に8~10年かかるなら、5年以内でできれば3年以内に一人前にできないかチャレンジする
ここまでいかなくても、少しで会社が強くなる為の考え方を変えて、具体的な行動を起こして下さい。
実際に私のクライアントでは既に実施しており、その成果も多く出て来ています。ぜひ、御社にも取り入れて、強い会社を作るように頑張ってみて下さい。
第6回目の「難易度の高い業務ほどOJTという名の人任せでなくポイントや教育方法を「研究」すべき」では、
●難易度が低い業務ほどマニュアル化(明確化)されているが、なぜか難しい業務ほど人任せの現実
●習得に時間がかかる(難易度の高い)業務ほど、ノウハウの現場の職人依存の現状
について述べてきました。
更に、機械化、システム化を誰でも購入できる資本力で決まります。ただ、お金があれば同じことができる、即ち差を付けづらくなります。差別化できる事としては、人間が行う難易度の高い業務しかないのですが、マニュアル化しづらいので、教育方法の研究に力を入れている会社が少ないです。
ぜひ考え方だけは、
●仕事をさせながら、教育する
↓
●教育しながら、仕事もさせる
●習得に8〜10年かかるから大変なんです
↓
●習得に8~10年かかるなら、5年以内でできれば3年以内に一人前にできないかチャレンジする
ここまでいかなくても、少しで会社が強くなる為の考え方を変えて、具体的な行動を起こして下さい。
実際に私のクライアントでは既に実施しており、その成果も多く出て来ています。ぜひ、御社にも取り入れて、強い会社を作るように頑張ってみて下さい。
第6回目の「難易度の高い業務ほどOJTという名の人任せでなくポイントや教育方法を「研究」すべき」では、
●難易度が低い業務ほどマニュアル化(明確化)されているが、なぜか難しい業務ほど人任せの現実
●習得に時間がかかる(難易度の高い)業務ほど、ノウハウの現場の職人依存の現状
について述べてきました。
更に、機械化、システム化を誰でも購入できる資本力で決まります。ただ、お金があれば同じことができる、即ち差を付けづらくなります。差別化できる事としては、人間が行う難易度の高い業務しかないのですが、マニュアル化しづらいので、教育方法の研究に力を入れている会社が少ないです。
ぜひ考え方だけは、
●仕事をさせながら、教育する
↓
●教育しながら、仕事もさせる
●習得に8〜10年かかるから大変なんです
↓
●習得に8~10年かかるなら、5年以内でできれば3年以内に一人前にできないかチャレンジする
ここまでいかなくても、少しで会社が強くなる為の考え方を変えて、具体的な行動を起こして下さい。
実際に私のクライアントでは既に実施しており、その成果も多く出て来ています。ぜひ、御社にも取り入れて、強い会社を作るように頑張ってみて下さい。
第6回目の「難易度の高い業務ほどOJTという名の人任せでなくポイントや教育方法を「研究」すべき」では、
●難易度が低い業務ほどマニュアル化(明確化)されているが、なぜか難しい業務ほど人任せの現実
●習得に時間がかかる(難易度の高い)業務ほど、ノウハウの現場の職人依存の現状
について述べてきました。
更に、機械化、システム化を誰でも購入できる資本力で決まります。ただ、お金があれば同じことができる、即ち差を付けづらくなります。差別化できる事としては、人間が行う難易度の高い業務しかないのですが、マニュアル化しづらいので、教育方法の研究に力を入れている会社が少ないです。
ぜひ考え方だけは、
●仕事をさせながら、教育する
↓
●教育しながら、仕事もさせる
●習得に8〜10年かかるから大変なんです
↓
●習得に8~10年かかるなら、5年以内でできれば3年以内に一人前にできないかチャレンジする
ここまでいかなくても、少しで会社が強くなる為の考え方を変えて、具体的な行動を起こして下さい。
実際に私のクライアントでは既に実施しており、その成果も多く出て来ています。ぜひ、御社にも取り入れて、強い会社を作るように頑張ってみて下さい。
第6回目の「難易度の高い業務ほどOJTという名の人任せでなくポイントや教育方法を「研究」すべき」では、
●難易度が低い業務ほどマニュアル化(明確化)されているが、なぜか難しい業務ほど人任せの現実
●習得に時間がかかる(難易度の高い)業務ほど、ノウハウの現場の職人依存の現状
について述べてきました。
更に、機械化、システム化を誰でも購入できる資本力で決まります。ただ、お金があれば同じことができる、即ち差を付けづらくなります。差別化できる事としては、人間が行う難易度の高い業務しかないのですが、マニュアル化しづらいので、教育方法の研究に力を入れている会社が少ないです。
ぜひ考え方だけは、
●仕事をさせながら、教育する
↓
●教育しながら、仕事もさせる
●習得に8〜10年かかるから大変なんです
↓
●習得に8~10年かかるなら、5年以内でできれば3年以内に一人前にできないかチャレンジする
ここまでいかなくても、少しで会社が強くなる為の考え方を変えて、具体的な行動を起こして下さい。
実際に私のクライアントでは既に実施しており、その成果も多く出て来ています。ぜひ、御社にも取り入れて、強い会社を作るように頑張ってみて下さい。
第6回目の「難易度の高い業務ほどOJTという名の人任せでなくポイントや教育方法を「研究」すべき」では、
●難易度が低い業務ほどマニュアル化(明確化)されているが、なぜか難しい業務ほど人任せの現実
●習得に時間がかかる(難易度の高い)業務ほど、ノウハウの現場の職人依存の現状
について述べてきました。
更に、機械化、システム化を誰でも購入できる資本力で決まります。ただ、お金があれば同じことができる、即ち差を付けづらくなります。差別化できる事としては、人間が行う難易度の高い業務しかないのですが、マニュアル化しづらいので、教育方法の研究に力を入れている会社が少ないです。
ぜひ考え方だけは、
●仕事をさせながら、教育する
↓
●教育しながら、仕事もさせる
●習得に8〜10年かかるから大変なんです
↓
●習得に8~10年かかるなら、5年以内でできれば3年以内に一人前にできないかチャレンジする
ここまでいかなくても、少しで会社が強くなる為の考え方を変えて、具体的な行動を起こして下さい。
実際に私のクライアントでは既に実施しており、その成果も多く出て来ています。ぜひ、御社にも取り入れて、強い会社を作るように頑張ってみて下さい。
第6回目の「難易度の高い業務ほどOJTという名の人任せでなくポイントや教育方法を「研究」すべき」では、
●難易度が低い業務ほどマニュアル化(明確化)されているが、なぜか難しい業務ほど人任せの現実
●習得に時間がかかる(難易度の高い)業務ほど、ノウハウの現場の職人依存の現状
について述べてきました。
更に、機械化、システム化を誰でも購入できる資本力で決まります。ただ、お金があれば同じことができる、即ち差を付けづらくなります。差別化できる事としては、人間が行う難易度の高い業務しかないのですが、マニュアル化しづらいので、教育方法の研究に力を入れている会社が少ないです。
ぜひ考え方だけは、
●仕事をさせながら、教育する
↓
●教育しながら、仕事もさせる
●習得に8〜10年かかるから大変なんです
↓
●習得に8~10年かかるなら、5年以内でできれば3年以内に一人前にできないかチャレンジする
ここまでいかなくても、少しで会社が強くなる為の考え方を変えて、具体的な行動を起こして下さい。
実際に私のクライアントでは既に実施しており、その成果も多く出て来ています。ぜひ、御社にも取り入れて、強い会社を作るように頑張ってみて下さい。
第6回目の「難易度の高い業務ほどOJTという名の人任せでなくポイントや教育方法を「研究」すべき」では、
●難易度が低い業務ほどマニュアル化(明確化)されているが、なぜか難しい業務ほど人任せの現実
●習得に時間がかかる(難易度の高い)業務ほど、ノウハウの現場の職人依存の現状
について述べてきました。
更に、機械化、システム化を誰でも購入できる資本力で決まります。ただ、お金があれば同じことができる、即ち差を付けづらくなります。差別化できる事としては、人間が行う難易度の高い業務しかないのですが、マニュアル化しづらいので、教育方法の研究に力を入れている会社が少ないです。
ぜひ考え方だけは、
●仕事をさせながら、教育する
↓
●教育しながら、仕事もさせる
●習得に8〜10年かかるから大変なんです
↓
●習得に8~10年かかるなら、5年以内でできれば3年以内に一人前にできないかチャレンジする
ここまでいかなくても、少しで会社が強くなる為の考え方を変えて、具体的な行動を起こして下さい。
実際に私のクライアントでは既に実施しており、その成果も多く出て来ています。ぜひ、御社にも取り入れて、強い会社を作るように頑張ってみて下さい。
第6回目の「難易度の高い業務ほどOJTという名の人任せでなくポイントや教育方法を「研究」すべき」では、
●難易度が低い業務ほどマニュアル化(明確化)されているが、なぜか難しい業務ほど人任せの現実
●習得に時間がかかる(難易度の高い)業務ほど、ノウハウの現場の職人依存の現状
について述べてきました。
更に、機械化、システム化を誰でも購入できる資本力で決まります。ただ、お金があれば同じことができる、即ち差を付けづらくなります。差別化できる事としては、人間が行う難易度の高い業務しかないのですが、マニュアル化しづらいので、教育方法の研究に力を入れている会社が少ないです。
ぜひ考え方だけは、
●仕事をさせながら、教育する
↓
●教育しながら、仕事もさせる
●習得に8〜10年かかるから大変なんです
↓
●習得に8~10年かかるなら、5年以内でできれば3年以内に一人前にできないかチャレンジする
ここまでいかなくても、少しで会社が強くなる為の考え方を変えて、具体的な行動を起こして下さい。
実際に私のクライアントでは既に実施しており、その成果も多く出て来ています。ぜひ、御社にも取り入れて、強い会社を作るように頑張ってみて下さい。