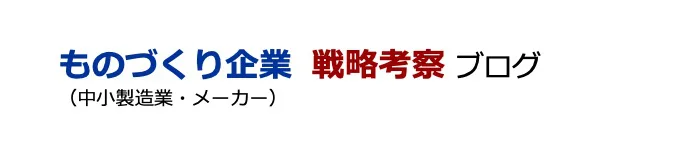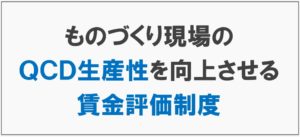製造業経営コンサルタントの井上です。
6月1日に最高裁で非正規社員、定年後再雇用の待遇格差に関する判決が出されました。
今後の方向性が示されたというとこでしょうか。
判決は、冷静に考えればその通り。経営側から考えれば、冗談じゃないというところでしょうか。
まず内容を見ていきましょう。
【非正規労働訴訟】
「非常に悲しい報告」 長沢運輸原告「理不尽判決」に怒り「同一労働同一賃金」が議論される中、非正規社員と正社員の待遇格差をめぐる2つの訴訟で、最高裁が1日、初の判断基準を示した。「同じ仕事なのになぜ…」「喜ばしい」。定年後再雇用の格差容認の判断に原告が落胆する一方、主張の大部分が認められた原告は喜びを見せた。(産経ニューるより)
主に手当の関係と定年後再雇用の条件の違いに関することです。
まず手当に関しては、
●精勤手当
●無事故手当
●作業手当
●給食手当
●皆勤手当
●通勤手当
上記、6つは非正規社員に対しても、正社員と同様に払わないと不合理と判断されました。
正直なところ、今どき通勤手当以外の手当てが存在することが、経営体質がそもそも古いのでは?と感じます。
ただ、運送会社に対してということですので、業務の内容が人的により作業系の仕事であるという前提であることは理解できます。
私のクライアントの業界である製造業も業種によりますが、似たようの手当てがあることは事実です。
現状、賃金制度を変えていることろが多く、今回の判決を受けて変更を迫られます。
私の考えでは、手当はなるべく減らし、賞与に振っていくことが、業績を上げるツールとしての賃金評価制度という観点から言っても重要になってきます。しかし、賃金の決め方(例えば、職務要件)や賞与の決め方(例えば、評価項目)などがファジーすぎる会社が多すぎます。しっかりと働いて欲しいと思い口酸っぱく、上司が指示や命令をしている状況でも評価があいまいすぎる会社がなんと多いことか。。。
頑張る社員が報われるような会社になることを切望しますね。
次に、定年後再雇用の待遇格差に関する判決は、合理性ありとの判断。
これは社員側が喜びそうですが、原告側は定年している人ということは、給料が比較的高い状態で定年を向かえている人たちということになります。
現状は、中小企業の場合、バブル景気などを経て50~55才以降の人は非常に給与が高い状態のまま、現在まで来ています。
経営者が給与は下げられないという考えのもと、給与が高い水準に据え置かれ、そのつけが若手の社員の給与に来ています。
これからは「同一労働同一賃金」に向かっていくので、仕事によっては年齢に関係なく30歳代で給与が昇給しない仕事をどんどんでてくると思います。
難し仕事・付加価値を生む仕事は給与が上がり、作業系で数か月で習得できる仕事は給与水準が下がっていくことでしょう。
ただ産業財製造業はしばらく仕事が多くあり、中小企業でも収益性があがるので、給与が比較的下がりにくい、逆に上がっていく傾向にあるので、若い人にも人気の業種に徐々になるのでは?と1~2年前から思っています。